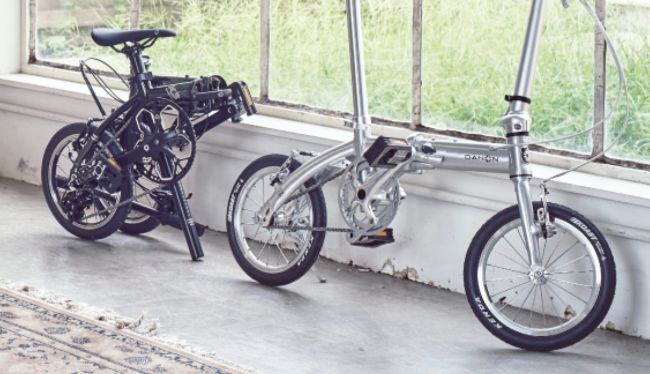読む
【サイクルツーリズム】大阪府能勢町と豊中市のサイクリスト職員に訊く観光施策と環境施策
2021.03.22

2018年に「自転車活用推進計画」が閣議決定され、都道府県および市町村は地域の実情に応じた自転車の活用の推進に関する施策を定める努力をすることになったが、自転車活用推進計画の策定や、能動的な自転車の活用に取り組んでいる地方自治体には大きな偏りが見られる。今回は、これから自転車を活用した観光地域づくりやインフラの整備を検討していくごく一般的な地方自治体の例として大阪府の能勢町を、自転車活用推進計画(令和3年1月策定)作成の例として同じく大阪府の豊中市をピックアップし、能勢町は地域振興課の井上良介さんに、豊中市は環境政策課の豊田泰則(やすのり)さん、水島文彦(のりよし)さんに、それぞれの自治体におけるサイクルツーリズムへの対応状況や課題、また地域の魅力について伺った。
能勢町と豊中市

大阪府の最北端に位置する能勢町は、梅田から車で50分程度と気軽に行ける距離にありながら、四方を自然豊かな山に囲まれ気温が5℃ほど低く、大阪の避暑地として知られている。農林水産省の日本の棚田百選に認定されている「長谷の棚田」、国天然記念物の「野間の大ケヤキ」、一万年の間続いているブナ林を中心とした原生林を筆頭に日本の原風景が広がり、美しい緑、澄んだ清流、新鮮な空気を堪能できる地域だ。能勢町では、住民生活の利便性を向上させながら、田園景観と豊かな自然を守り続ける取り組みをされている。
一方、大阪市に隣接し府内第4位の人口を擁する豊中市は、北部中部に高級住宅地、南部に商工業地域が広がり、市の全域が市街化された中核市だ。郊外と都心部、観光地と住居地、交通が既に発達し道路環境の整備に制約がある所とこれから整備できる所など、自転車を取り巻く環境も対照的な自治体といえる。

——皆さんはスポーツバイクに乗られているそうですが、興味をもたれたきっかけは何だったのですか。
井上さん:運動不足を感じていた時に、ちょうど豊田さん、水島さんと業務で知り合いになり、スポーツバイクのお話を楽しそうにされていたので、興味が湧きました。ロードバイクを購入したばかりですが、能勢町内や淀川サイクリングロードなどを走っています。
水島さん:ロードバイクを乗り始めたのは、太ってきたので夜にランニングを始めたのがきっかけですね。当時はオートバイで通勤していましたが、通勤時も運動すれば効率が良いと思い1週間に2日程度自転車(シティサイクル)で通っていました。しばらくはそんな感じで通勤していましたがバイクも燃料代がかかるので、自転車ならかからないと思い自転車通勤に変更し、その際にクロスバイクを購入しました。スポーツバイクらしい走り、楽に前に進むことに驚き感動しました。このクロスバイクならどこまで行けるのか気になり始めて少しずつ距離が伸び、琵琶湖を一周するまでになりました。現在はロードバイクに買い替え、最近では出雲大社まで自走で行きました。
豊田さん:通勤に使っていた自転車の買い替えを機に、職場の同僚の勧めもありクロスバイクに乗り換えました。
——なるほど、井上さんから業務を通じてお二人と知り合われたと伺っていましたが、そういう経緯だったのですね。水島さんの、出雲大社までと言うのは驚きました。皆さんはそれぞれの役場で、どのようなお仕事をされているのですか?
井上さん:能勢町の地域振興課に所属し、農林業の振興や、都市部との交流事業等に取組んでいます。
豊田さん:二人とも豊中市の環境部環境政策課に所属し、環境分野のベースとなる環境基本計画の進行管理や温暖化対策、開発行為への緑化協議などを担当しています。

——能勢町と豊中市、異なる自治体に勤める皆さんは「街と里の持続可能な連携の仕組みづくり」に一緒に取組んでおられるようですが、どのような取組みなのでしょうか。
井上さん:能勢町は、希少な生きものが多数生息・生育し豊かな生物多様性が保たれた地域です。これは能勢町の特産品である栗栽培や、椎茸のほだ木づくりをはじめとする里山の活用によって里山が維持されてきた結果です。しかし、能勢町では高齢化や、人口減少により管理されない里山が増えてきました。それを豊中市等の都市部自治体と連携し、経済性を伴って解決していこうという取組みです。
豊田さん:本市と能勢町は、一級河川である猪名川の上流部と下流部の位置関係を有するほか、本市の消防署の分署が能勢町内にあることや能勢町の北東部の山間地に本市が昭和37年に市立青少年自然の家「わっぱる」を設置し、青少年に自然や野外活動の場を提供しているといった関係性が築かれています。市域全域が市街化区域であり、活動を行うフィールドが不足していることから、能勢町における地域の生物多様性の保全再生等に資することを目的に設置された「能勢の里山活力創造推進協議会」に参加しています。本市は、都市部と農村地域の経済性を伴った持続的な交流活動事例に関心をもち、都市住民の行動変容、農山村の自然環境の育みや地域経済の振興、また、次世代を担う人材育成につながるものと考え、協議会で実施している「里山DAYキャンプ」に参加しています。
——そんなにたくさんの関わり、連携があるのですね。驚きました。能勢には銀寄という栗、能勢菊炭という炭など、他には無いブランドがあるのも強みですね。自然が多く残る自治体はたくさんあると思うのですが、豊中市から見た能勢町の魅力というのはどのようなものでしょうか。

豊田さん: 能勢町さんは、民間シンクタンクが発表した「生物多様性に優れた自治体ランキング」の指標1(緑地等の現況:都市における生物多様性確保のポテンシャルを有する緑地等の割合)で1位になったことに象徴されるとおり、大都市近郊にも関わらず、能勢町の里山には豊かな生態系が維持されています。
——なるほど、気候変動対策や自然環境保全について考えると、単に緑が多いだけではなく生物多様性や生態系の維持といった視点も確かに大切ですね。
観光と自転車
——能勢町の観光について調べていると、能勢なつかしさ推進協議会の、地域の伝統や歴史を残しながら過疎に向かいつつある地元の活性化や、移住者の受け入れ対策等の地元民と観光のコラボなどに共感しました。観光客の増加は地域活性化に繋がりますが闇雲に観光客を誘致するのではなく、都心部に近い立地である能勢らしい取り組みだと思います。町や地域団体の取り組みとしては他にどのようなことが行われていますか?
井上さん:町としては、都市部の自治体や企業に、CSR活動の場として能勢町の栗林や、森林を借り上げてもらうことを計画しています。例えば午前中に里山管理の活動をしていただき、午後からは町内の観光地やレストラン、キャンプ場などを満喫していただくようなパッケージ作りを行わなければならないと考えています。

——急に最近になってSDGsが世間で知られるようになり、弊社もですがCSR活動の推進に力を入れ始める企業が増えています。企業は自分達にできること、すべきことを模索しているので、地域と企業が結びつくのにちょうどいいタイミングだと思います。
ところで近年、サイクルツーリズムを地方創生に生かす動きが顕著になってき ました。現在の能勢における取り組みがあれば、教えてください。
井上さん:まず前提として、京阪神からの車によるアクセスには優れるものの、電車は乗り入れていないので、週末の気軽なドライブ先としてのイメージが強いという状況があります。一方で自転車については、レンタサイクルサービスには以前から取り組んでおり、ロードバイクで走りに来られる方も案外おられることからサイクルラックの設置場所は増やしていますが、走行環境の整備やサイクリスト向け情報発信、自転車イベントの誘致などまでは至っていません。
——能勢は史跡や棚田からパワースポットやお洒落な店まで観光資源が豊富なので、目的を変えて何度も訪れるような場所ですよね。個人的な話ですが私も昨年は特に密を避けるという状況もあり、4回くらい家族で行きました。新鮮な農産物の直売目当てに道の駅に行ったついでに…ということも多いですけど(笑)。豊田さんや水島さんも能勢を自転車で走られることがあるのですか?
水島さん:私も能勢町には車でドライブがてらお洒落な店をさがして、よく行かせていただいています。もともとドライブが好きで茨木や高槻などに行っています。1人で行くときは自転車でも行きますが、峠を越えないといけないのが辛いですね。能勢町の自然が多くのんびりした感じがとても好きです。
——ロードバイクでのサイクリングには、一定の速度で走りやすい能勢町の環境がちょうど良いですが、豊中市でも市内の名所旧跡、観光・絶景スポットを巡る「散走ルート」を検討されているそうですね。やはり自転車は環境にも優しい点からも注目を集めていると思いますが、環境政策課から見ていかがでしょうか。
豊田さん :本市のサイクリングロード計画は、市内に点在する親水空間やみどりの空間を結び、サイクリングやウォーキングで回遊できるネットワークを整備することを目的として、平成6年に策定しています。千里中央公園から服部緑地、高川、神崎川および猪名川等を結ぶ計画であり、全体構想のうち、千里緑地ルートは平成12年度に完成していますが、現在は計画が止まっています。一方で全体的なネットワークとして、自転車通行空間の整備を進めていますので、これらを活かし、市内の名所、観光スポットを巡る「散走ルート」を今後検討したいと考えています。本市は、土地の起伏が少なく自転車が使いやすい特徴を活かし、自転車等の利用を促進しています。自転車は自動車などと異なり、ガソリンなどの化石燃料を必要としないことからCO2排出量がゼロであり、環境にやさしい乗り物として推奨しています。
——能勢町では地域全体に観光スポットが点在しているので自転車で巡るのに向いており、交通量や信号も多くないので自転車に乗ることそのものを楽しむこともできます。周辺都心部からロードバイクで走りに来る層も一定数いますが、スポーツバイクが趣味ではない一般観光客向けレンタサイクルの稼働状況はいかがですか?
井上さん:週末を中心にスポーツバイクで来られる方を多く見かけます。私自身も能勢町は非常に走りやすいと思います。レンタサイクルについては、スポーツバイクでは無く、電動アシスト付きの自転車になりますが、年間100回程度の貸出があります。
——ここ数年、全世界的にeBike(電動アシスト付きスポーツ自転車)が爆発的に普及してきています。能勢町は峠を挟んで幾つかの地域に分かれているので、広域的な移動や、妙見山など山そのものへ登る走り方を前提にeBikeを導入すると一層楽しみが広がると思います。将来的にそのような動きは考えられますか?
井上さん:まずは、能勢町で試乗イベント等が出来れば面白いのではないかと思います。能勢町では10月に「てっぺんフェスティバル」という秋のお祭りがあり、多くの方は町内外から来場されます。そこで試乗用のコースを設定し、試乗イベントを行えば面白いのではないでしょうか。
——アキボウもCSR活動と絡めて能勢町のサイクリングコースの紹介や試乗会に取り組もうとしていますしね。
豊田さん:私は、クロスバイクを乗っていて、今はやりのeBikeがすごく気になっています。
水島さん:eBikeは、脚力の弱い人でも上り坂が無理なく走行できるのが魅力的です。
——そうですね、eBikeなら可能性が広がりますね。試乗会で実際に体験することで、多くの方に知っていただければと思います。

インフラとしての自転車
——「散走」の話は上で出ましたが、豊中市では市民の皆さんの日常生活における身近な移動手段として自転車の利用が既に多くあり、更に密を避ける移動手段としてや、在宅勤務の広まりとともに問題となった運動不足の解消法としても注目されています。自転車人口の増加に対しては交通ルールの周知とともに、安全な自転車通行空間の整備も急がれますが、現状どういった進捗状況にありますか?

豊田さん:本市の自転車通行空間整備の推進は、歩行者と自転車利用者にとって、安心・安全に移動できる環境整備を図るため、平成31年2月に策定した「豊中市自転車ネットワーク計画」に基づき、自転車通行空間の整備を進めています。自転車の安全で快適かつ便利な利用環境の整備とともに通行ルールの順守を促し秩序ある交通環境の確保をはかるとした基本理念のもと、平成31年度から5か年で25kmを整備する目標を立てています。
——自転車は健康にも自然環境の維持にも有効なので、無理なく広がっていけばいいですね。

長期的な展望
——2018年に設立された「自転車を活用したまちづくりを推進する全国市区町村長の会」への大阪府下の自治体の加入状況は、43市町村のうち8つの自治体と、とても少ない状況です。一方、アクセスや観光資源など条件は様々ですが、サイクリングルートの開発といえば、しまなみ海道サイクリングロードを筆頭に、つくば霞ヶ浦りんりんロード、ビワイチが注目を浴びており、関西に限って言えばビワイチの他には淡路島(アワイチ)、和歌山県、京都府北部、奈良県などで道路環境や受け入れスポットの整備が進んでいます。それらとは目指すところは違っても、能勢町と豊中市では自転車を活用してどのようなことから取り組んでいけると思われますか?
井上さん:能勢町でも昨年の9月に能勢町観光協会が発行した冊子にレンタサイクルコースを掲載するなど、地道ではありますがサイクルツーリズムに繋がればと考えています。町内では多くのカフェや、レストランが近年オープンしており町外から多くの方がお越しになられています。サイクルラックの設置状況などを調査し、多くのモデルコースを作れば何度も能勢町に行ってみようと思ってもらえるのでは無いかと考えています。
豊田さん:自転車の活用は、自動車から自転車への転換を促すことにより、市域の道路における渋滞が緩和され、CO2排出量の抑制が図られます。また、自転車を利用することによって、健康づくりや余暇の充実が図られ、地域や仲間とのつながりを深めることができます。このようなことから、その利用促進に向けた啓発を実施しています。市域での自転車利用に物足りなくなり、スポーツ自転車に興味を持つ市民へ能勢町の魅力を発信し、環境負荷の少ない余暇の過ごし方や自然環境の豊かさを学び、温暖化対策の取組みが一歩でも前進するような普及啓発を行っていきたいと考えています。
——日本で自転車というとシティサイクルを基準とした短距離移動のイメージが強く、例えば広域的に都市間を結ぶために高速で走行できる専用レーンを整備しよう、といった方向にはなかなか進みづらいようですが、行政で働かれている方の中にもスポーツバイクの素晴らしさを知る方が増えることで、ヨーロッパの自転車先進国に近づければいいなと思います。
自転車で巡るおすすめスポット
——先の話にも出ましたが、能勢町、豊中市それぞれで、自転車で巡れるスポットを教えてください。能勢町ではまずは能勢町観光物産センターとして機能している「道の駅 能勢(くりの郷)」を起点にするのがメジャーでしょうか。町内で生産・収穫された新鮮な農産物を買える農産物直売コーナーは私も家族で何度も利用しています。
井上さん:能勢町は大阪市内からも車であれば1時間程度でお越し頂けるので、非常にアクセスにも優れています。「道の駅 能勢(くりの郷)」では、地元で獲れた新鮮な農産物を販売していますし、地元の農産物を提供するレストランもあります。昨年の秋には能勢産のお米を使用したおにぎりショップも新たにオープンする等サイクリングの拠点や目的地にぴったりです。また最近、新たにサイクルラックも設置しました。

——町内は豊かな自然に恵まれ、それだけでも素晴らしいのですが、観光スポットとしてはやはり「野間の大けやき」は外せませんよね。資料館で見た太い木の幹には驚きました。
井上さん:「野間の大けやき」は樹齢1,000年以上と推定され、能勢町の樹木のシンボルにもなっています。「けやき資料館」も併設されていますので、見学頂ければ「野間の大けやき」について多くのことを知って頂けます。ここにもサイクルラックがありますので、週末を中心に多くのサイクリストの方が「野間の大けやき」を見ながら休憩されています。


——豊中市は個人的にも馴染みがあるのですが、自転車でのアクセスとしては千里川土手から望む大阪国際空港の風景が有名ですね。豊中市の自転車活用推進計画(概要版)でも「市内における散走のイメージ」として掲載されています。



——それでは最後に。皆さん、サイクリストの立場としては、将来的に日本の都市部での自転車環境はどうなれば良いとお考えですか。
皆さん:レジャースポーツ的な視点では、しまなみ海道のような観光スポットだけでなく、例えば豊中市から能勢町へも自転車で安全にアクセスできるように自転車レーンがしっかり整備され、途中に何ヵ所か休憩に立ち寄れる施設などがあれば最高ですね。
今回は、自転車を活用した観光地域づくりやインフラの整備を今後検討していくごく一般的な地方自治体の例として大阪府の能勢町と豊中市をピックアップし、それぞれの自治体におけるサイクルツーリズムへの対応状況や課題、また地域の魅力について伺った。
昨年からのコロナ禍で自転車通勤が注目されているが、自転車の有用性は京都議定書の採択が発端となった1997年のエコブーム、2005年のメタボリックシンドロームブーム、原油価格が高騰した2008年、2011年の東日本大震災と、これまでに何度も認識されているが、欧米の取り組みに比べると日本における自転車環境は大きく遅れをとっている。
既に市街化された街なかでの新たな自転車通行空間の確保や、豊かな自然を守りながらの整備などは困難なことが容易に想像できるが、観光施策や環境施策における自転車の更なる活用を、全国の行政の現場におられるサイクリストの皆さんに期待したい。
*この記事で紹介している情報は、2021年3月時点の取材に基づいています。
*参考資料
国土交通省自転車活用推進計画
大阪府自転車活用推進計画
豊中市自転車活用推進計画
*参考リンク
能勢町の観光と物産「のせNOTE」
能勢町観光ガイドブック「のせCAN」(PDF)
ITEM コラムで紹介した商品
#LINZINEの最新記事